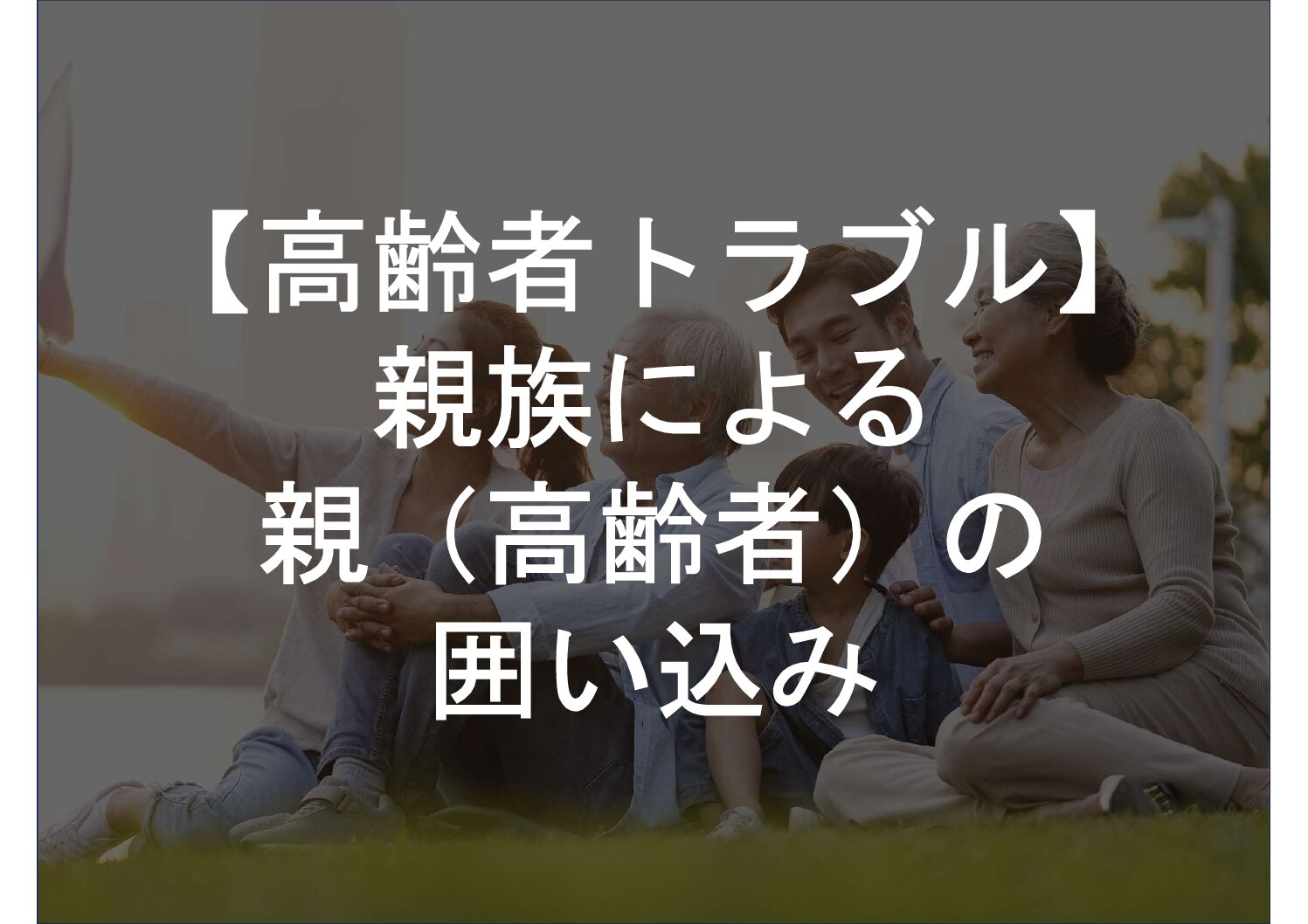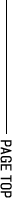Contents
下請法:親事業者の義務・禁止行為を基礎から徹底解説!
下請法の役割
独占禁止法の補完
中小企業保護
公正な取引の実現
親事業者の義務
書面の交付義務(第3条)
支払期日を定める義務(第2条の2)
書類の作成・保存義務(第5条)
遅延利息の支払義務(第4条の2)
親事業者の禁止事項
受領拒否(第4条第1項第1号)
(1)規定のねらい
(2)「受領を拒む」とは
(3)受領拒否が認められる「下請事業者の責めに帰すべき理由」とは
支払遅延(第4条第1項第2号)
(1)規定のねらい
(2)支払遅延
(3)受領日
減額(第4条第1項第3号)
(1)規定のねらい
(2)減額が認められる「下請事業者の責めに帰すべき事由」
(3)代金減額の例
(4)代金減額に当たらない場合
返品(第4条第1項第4号)
(1)規定のねらい
(2)返品が認められる「下請事業者の責めに帰すべき事由」
(3)返品可能期間
買いたたき(第4条第1項第5号)
(1)規定のねらい
(2)「買いたたき」(5号)と「減額」(3号)の違い
(3)「通常支払われる対価に比して著しく低い下請代金の額」とは
購入・利用強制(第4条第1項第6号)
(1)規定のねらい
(2)「自己の指定する物」又は「役務」
(3)「強制して」購入させる又は利用させるとは
(4)購入・利 用強制に当たるおそれのある行為例
報復措置(第4条第1項第7号)
最後に
下請法:親事業者の義務・禁止行為を基礎から徹底解説!
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、下請事業者を守るための重要な法律です。親事業者の優越的な立場を利用した不当な行為を規制し、下請事業者が安心して取引できる環境を整備することを目的としています。
下請法違反に対しては、公正取引委員会による立入検査、勧告、排除措置命令、課徴金納付命令、違反事実の公表、さらには法人及び個人に対する罰則の規定が適用される可能性もございます。
本稿では、下請法に規定される親事業者の義務を紹介し、続いて、公正取引会が公表する考え方を踏まえ、親事業者の禁止行為につき、その判断方法のほか、禁止行為の具体例を挙げて詳しく解説していきます。
親事業者におかれましては、下請法の内容について今一度ご確認を頂き、思わぬところで下請法違反に問われないよう、日頃より法令遵守を心掛けた取引を行って頂きたいと思います。
また、下請事業者におかれましては、いかなる行為が下請法に違反するかをご理解頂き、自らの利益を守るため、後述しますとおり専門家にご相談を頂くなど適切な対応につなげて頂ければ幸いです。
下請法の役割
まず、下請法の役割についてまとめると以下のとおりです。
独占禁止法の補完
独占禁止法は優越的地位の濫用を規制していますが、その該当性を判断するためには、個別の状況を考慮しなければならないため時間を要します。
親事業者の優越的地位を濫用した行為により利益が害されている下請事業者の救済に時間を要しては、下請事業者が事業活動を維持すること自体困難となってしまいます。
そのため、下請法は、具体的な行為類型を定め、親事業者の不当な行為を防止し、下請事業者を迅速に救済しようとするものです。
中小企業保護
下請事業者の多くは中小企業であり、親事業者との力関係で不利な立場に置かれがちです。下請法は、親事業者の義務と禁止事項を具体的に定めることにより、中小企業の利益を守り、健全な下請取引を促進しようとするものです。
公正な取引の実現
下請法は、親事業者に対し、支払遅延、不当な減額、買いたたきなどの具体的な行為を禁止しています。これにより、下請事業者が適正な対価を受け取り、安心して事業活動を継続できる環境を実現しようとするものです。
親事業者の義務
下請法は、親事業者に対し、以下の4つの義務を課しています。
書面の交付義務(第3条)
・親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合には、直ちに、後述の必要事項を記載した発注書面(以下「3条書面」といいます。)を交付しなければなりません。
・3条書面には、下請代金の額、支払期日、給付の内容、給付の受領期日、検査の有無、代金の支払方法などを記載する必要があります。
【具体的記載事項】
①親事業者及び下請事業者の名称
②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③給付の内容
④給付を受領する期日
⑤給付を受領する場所
⑥給付内容につき検査をする場合は、検査完了日
⑦下請代金の額
⑧下請代金の支払期日
⑨手形を交付する場合は、その手形の金額及び手形の満期
⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は 支払を受けることができることとする額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
⑫原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
・下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難な場合においても(やむを得ない事情があることを要します)、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載する必要があります。
・必要記載事項のうちその内容が定められないことに正当な理由がある場合には、一定の例外が認められていますが、記載事項が不足している場合や、交付が遅れた場合には義務違反となります。
・書面交付義務、後述の書類作成・保存義務に違反した親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処するとの罰則規定が定められています(第10条)。
支払期日を定める義務(第2条の2)
・親事業者は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、受領日から起算して60日以内(受領日を算入)のできる限り短い期間内で、下請代金の支払期日を定める義務があります。
【受領日】
製造・情報成果物作成委託:納品物を受領した日
役務提供委託;役務を提供した日
・親事業者は、下請代金の支払期日を、給付の受領後60日以内で、かつ、できる限り短い期間となるように定めなければなりません。
・支払期日を定めなかったり、60日を超える期日を定めたりすることは、義務違反となります。この場合、受領日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなされます。
書類の作成・保存義務(第5条)
・親事業者は、下請取引に関する書類(発注書、見積書、納品書、請求書、支払明細書など)を作成し、2年間保存しなければなりません。
・上記書類には、以下の事項を具体的に記載することが義務付けられております。
【具体的記載事項】
①下請事業者の名称
②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③給付の内容
④給付を受領する期日
⑤受領した給付の内容及び給付を受領した日
⑥給付の内容につき検査をした場合は、検査完了日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
⑦給付の内容につき変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由
⑧下請代金の額(算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変 更後の算定方法により定まった下請代金の額及び変更した理由)
⑨下請代金の支払期日
⑩下請代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
⑪支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
⑫手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
⑬一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から 貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権 相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
⑭電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権 の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日
⑮原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
⑯下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下 請代金の残額
⑰遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
遅延利息の支払義務(第4条の2)
・親事業者は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者に対し、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ遅延利息を支払う義務がある。
・遅延利息は、未払代金に対して年率14.6%が発生することが定められています。
親事業者の禁止事項
下請法では、下請事業者を保護するために、親事業者に対して11の禁止事項を定めています。これらの行為は、たとえ下請事業者の同意があっても、また親事業者が違法性を認識していなくても、法律違反となりますますので、ご留意ください。
なお、役務(サービス)を提供する委託業務の発注では、「受領拒否」と「返品」は禁止事項から除かれています(下請法4条1項本文括弧書)。
1 受領拒否(第4条第1項第1号)
2 支払遅延(第4条第1項第2号)
3 減額(第4条第1項第3号)
4 返品(第4条第1項第4号)
5 買いたたき(第4条第1項第5号)
6 購入・利用強制(第4条第1項第6号)
7 報復措置(第4条第1項第7号)
8 代金支払前の原材料等の対価請求(第4条第2項第1号)
9 割引困難な手形交付 (第4条第2項第2号)
10 不当な経済上の利益の提供要請(第4条第2項第3号)
11 不当な内容変更及びやり直し(第4条第2項第4号)
以下、本稿では、上記11の禁止行為のうち、下請法4条1項各号で定める7つの禁止行為について詳述していきます。
受領拒否(第4条第1項第1号)
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと」
(1)規定のねらい
・製造委託物は特殊な場合が多く、他への転売が困難。
・受領拒否されると下請事業者の損失が大きい。
・下請事業者の利益保護を目的として、不当な受領拒否を禁止。
(2)「受領を拒む」とは
・給付の全部または一部を納期に受け取らないこと。
・発注の取消(契約解除)・納期延期も、原則、受領拒否に含まれる。
(3)受領拒否が認められる「下請事業者の責めに帰すべき理由」とは
・受領拒否が認められるのは、以下の場合のみ。
ア 3条書面の委託内容と異なる
イ 給付に瑕疵がある
ウ 納品が3条書面の納期に遅延したため不要となった
※3条書面:親事業者が下請事業者に対して交付義務を負う委託内容、代金、支払期限・方法等を記載した書面(下請法第3条)
・ただし、以下の場合は受領拒否が認めらない。
ア 3条書面の委託内容と異なる場合、給付に瑕疵がある場合でも、
(ア)3条書面に委託内容の明記がない
(イ)検査基準が明確でない
(ウ)発注後に検査基準を厳格化
(エ)委託内容の変更を了承
イ 納品が3条書面の納期に遅延したため不要となったでも場合でも、
(ア)3条書面に納期が明記されていない
(イ)親事業者が原材料支給を遅滞
(ウ)無理な納期
支払遅延(第4条第1項第2号)
「下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」
親事業者は、給付内容を検査したか否かに拘わらず、受領日から60日以内で、出来るだけ短い期間で定めた支払期日までに代金全額を支払わなければ違法となります。
支払期日の経過後は、未払代金に対して14.6%の遅延損害金が発生しますのでご注意ください。
(1)規定のねらい
下請事業者の資金繰りの悪化を防止し、経営の安定化を図る。
(2)支払遅延
支払遅延の考え方は以下のとおりとされています。
ア 支払期日が受領日から60日以内・・・支払期日経過により支払遅延
イ 3条書面に支払期日の定めなし・・・受領日経過後により支払遅延
ウ 支払期日が受領日から60日を超える・・・受領日から60日経過により支払支援
(3)受領日
支払期日の起算日となる給付の受領日の考え方は以下のとおりとされています。
・受領日は「給付の受領」があった日
・製造・修理委託では、検査の有無に拘わらず、目的物を受け取り、自己の占有下に置けば「給付の受領」
・親事業査の検査員が下請事業者に出向き検査する場合、検査を開始すれば「給付の受領」
・情報成果物の「給付の受領」は、それを自己の支配下に置くこと
・役務提供の「給付の受領」は、役務が提供された日(日数を要する場合は終了日)
減額(第4条第1項第3号)
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」
発注時に定めた代金を減額することは禁止されています。
減額の名目、方法、金額の大小、時期にかかわらず、代金の減額は違法となります。
過去に違法とされた減額の名目は以下のとおりです。
【違反とされた減額名目】
「リベート」、「協賛金」、「協力金」、「センターフィー」、「値引き」、「協力値引き」、「一括値引き」、「歩引き」、「分引き」、「基本割戻金」、「協定販売促進費」、「特別価格協力金」、「販売奨励金」、「販売協力金」、「一時金」、「手数料」、「支払手数料」、「本部手数料」、「」物流手数料、「管理料」、「物流及び情報システム使用料」など
※「減ずること」には、親事業者に減額分を支払わせることも含まるとされています。
(1)規定のねらい
下請事業者の立場は弱く、代金が一旦決定されても後に減額の要請がされやすいが、下請業者がこれを拒否すること困難であり、これを防止する必要。
(2)減額が認められる「下請事業者の責めに帰すべき事由」
「下請事業者の責めに帰すべき事由」は以下の場合に限られるとされています。
ア 瑕疵の存在・納期遅れ等による受領拒否・返品が下請法に違反しない場合で、これに係る減額
イ 上記アの場合で、親事業者が受領拒否・返品をせずに、自ら手直しをしてこれに要した費用のうち客観的相当額の減額
ウ 上記アの場合で、瑕疵の存在・納期遅れ等による商品価値の低下が明らかであることによる客観的相当額の減額
(3)代金減額の例
ア 単価引下の合意後、旧単価発注分に新単価を遡及適用し、代金から差額分を減額
イ 消費税相当額の不払い
ウ 書面での合意なく、振込手数料を代金から減額
エ 振込手数料を名目とする実費を超えた減額
オ 親事業者の原材料の納品遅れ・無理な納期指定による納期遅れを理由とする減額
カ 端数切捨てによる支払
キ 手形払いを下請業者の希望で現金払いした際、短期調達金利相当額を超える額の減額
ク 親事業者の客先のキャンセル、市況変化等による不用品相当額の減額
ケ 販売協力の名目による減額
コ 単価引下げに応じない場合に一定割合や一定額を減額すること
カ 代金総額は維持したまま数量を増加すること
(4)代金減額に当たらない場合
以下の場合には代金を「減ずること」には当たらないとされています。
ア 弁済期にある商品の売買代金債権や貸付金等の債権を下請代金から差し引くこと
イ 書面による合意のもと振込手数料の実費を下請代金から差し引くこと
ウ 手形払いと定めたが下請事業者の要望で現金払いとした場合に短期調達金利相当額を差し引くこと
返品(第4条第1項第4号)
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること」
下請事業者の責めに帰すべき理由のない納品物の返品は違法です。
名目や数量の多寡を問わず、また、返品につき合意があったとしても、下請事業者の責めに帰すべき理由のない返品は違法となりますのでご注意ください。
(1)規定のねらい
・製造委託物は特殊な場合が多く、他への転売が困難。
・返品されると下請事業者の損失が大きい。
・下請事業者の利益保護を目的として、不当な返品を禁止。
(2)返品が認められる「下請事業者の責めに帰すべき事由」
以下の場合であり、かつ、後述の返品可能期間内での返品に限り違法とはされません。
ア 3条書面の委託内容と異なる
イ 給付に瑕疵がある
ただし、以下の場合は返品が認めらない。
ア 3条書面に委託内容の明記がない
イ 検査基準が明確でない
ウ 発注後に検査基準を厳格化
エ 検査を省略
オ 検査を行わず、かつ下請事業者に文書での委任もない
(3)返品可能期間
返品が可能な期間は、以下のとおりとされています。
ア 直ちに発見可能な瑕疵:原則、速やかに返品
イ 直ちに発見できない瑕疵:給付の受領後6か月以内
ただし、給付した製品につき、一般消費者に対して6か月を超えて保証する場合、その保証期間に応じ、最長1年以内であれば返品可
買いたたき(第4条第1項第5号)
「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」
発注に際して代金額を決定する際、発注内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めると違法となります。
(1)規定のねらい
親事業者が、下請事業者に対し、その地位を利用して、同種又は類似の給付に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を押し付けることで、下請事業者の利益が害されることを防止。
(2)「買いたたき」(5号)と「減額」(3号)の違い
「買いたたき」:発注する際に発生
「減額」:代金決定後に発生
(3)「通常支払われる対価に比して著しく低い下請代金の額」とは
ア 「通常支払われる対価」
=市価:同種類似の給付につき当該取引地域で一般に支払われる対価
イ 市価の把握が困難な場合
(ア)従前の給付と同種同類
→従前の給付の単価で計算された単価が「通常支払われる対価」
(イ)従前の給付と同種同類+主なコスト上昇が公表資料から把握可能
→据え置かれた下請代金額が「著しく低い下請代金の額」
ウ 「買いたたき」の該当性判断における考慮要素
(ア)代金額決定の際に十分な協議が行われたか
(イ)決定された対価が差別的か
(ウ)「通常支払われる対価」と当該対価との乖離状況
(エ)当該給付必要な原材料等の価格動向
エ 「買いたたき」に該当するおそれのある行為の例
(ア)多量発注前提の見積りを少量発注する場合にも適用して代金額を決定
(イ)見積り後に発注内容が増えたが、代金の見直しをせずに当初見積りで代金額を決定
(ウ)親事業者の予算単価のみを基準に一方的に市価より低い単価で下請代金を決定
(エ)短納期発注にも拘わらず、追加費用を考慮せずに下請代金を決定
(オ)合理的理由なく特定の下請事業者のみに差別的な下請代金を決定
購入・利用強制(第4条第1項第6号)
「下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること」
正当な理由がないのに、下請事業者に対し、親事業者の指定する物の購入又は役務の利用を強制し、その対価を負担させることは違法となります。
(1)規定のねらい
親事業者が自社商品やサービス等を下請事業者に押し付け販売することを防止。
(2)「自己の指定する物」又は「役務」
親事業者又は関連会社等が販売する物又は提供する役務。
例えば、保険、リース、インターネットプロバイダー等のサービスも含む。
下請事業者の購入対象とした特定の物・役務が全て含まれる。
自社の製品・サービスのみでなく、自社の取引先である特約店、卸売店又は自社の子会社・関連会社等の製品やサービスを含む。
(3)「強制して」購入させる又は利用させるとは
「強制して」購入させる又は利用させるには、以下の場合が含まるとされております。
ア 物の購入・役務の利用を取引の条件とする場合
イ 購入・利用しないことに不利益を与える場合
ウ 事実上、購入・利用を余儀なくさせていると認められる場合
※親事業者が任意の購入等を依頼したと思っても、下請事業者にとってはその依頼を拒否できなければ「強制して」に当たり得る。
(4)購入・利 用強制に当たるおそれのある行為例
ア 購買・外注担当者等の取引に影響を及ぼす者が購入・利用を要請
イ 下請事業者ごとに目標額・目標量を定めて購入・利用を要請
ウ 購入・利用しなければ不利益取扱いをする旨示唆した購入・利用を要請
エ 購入・利用を下請事業者が拒否した後も重ねて購入・利用を要請
オ 購入の申し出がないのに一方的に購入を要請する物品を送付
報復措置(第4条第1項第7号)
「親事業者が第1号若しくは第2号に掲げる行為をしている場合若しくは第3号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に 下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取 引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること」
下請事業者が親事業者の本法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して不利益な取扱いをすることは違法となります。
〇規定のねらい
下請事業者が親事業者の報復を恐れず公正取引委員会や中小企業庁に対し、親事業者の本法違反行為を申告できるようにする状況を確保すること。
最後に
下請法違反は、下請事業者の事業活動に重大な影響を与えるだけでなく、親事業者のコンプライアンス意識に問題があることを示すものであり、社会的信用を失墜させる行為でもあります。
違反があるものと疑われた場合、また、違反行為があったと認められた場合には、以下の措置が執られる可能性がございます。
1 公正引委員会・中小企業庁による立入検査
2 違反親事業者に対して違反行為の是正やその他必要な措置をとるべきことの勧告
3 勧告した場合における事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等の公表
4 勧告に従わない場合における排除措置命令・課徴金納付
5 違反行為者に対する罰則の適用
下請法違反の罰則は両罰規定であり、以下のような場合、代表者・行為者(担当者)個人が罰せられるほか、会社 (法人)も罰せられることになります(50万円以下の罰金)。
①書面の交付義務違反
②書類の作成及び保存義務違反
③報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告
④立入検査の拒否、妨害、忌避
親事業者におかれましては、下請法の規定を今一度ご確認を頂きまして、下請法遵守を徹底し、公正な取引を心がけて頂ければと存じます。
また、親事業者の下請法違反に直面されている下請事業者におかれましては、下請法に詳しい専門家の支援を受けながら、適切に自らの利益を守ることが重要です。
当事務所では、下請法に関するご相談や下請法違反への対応について豊富な経験を有する弁護士が、個別のご事情に沿った解決策をご提案させて頂きます。ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
下請法が適用される取引とは?!https://www.brainlawyers.jp/case_column/case_column_test09/
「優越的地位の濫用」とは?!:「優越的地位の濫用」を基礎から徹底解説!https://www.brainlawyers.jp/case_column/case_column_470/
Column コラム
注目記事ランキング
相談事例のカテゴリー
準備中です
コラムをもっと見る