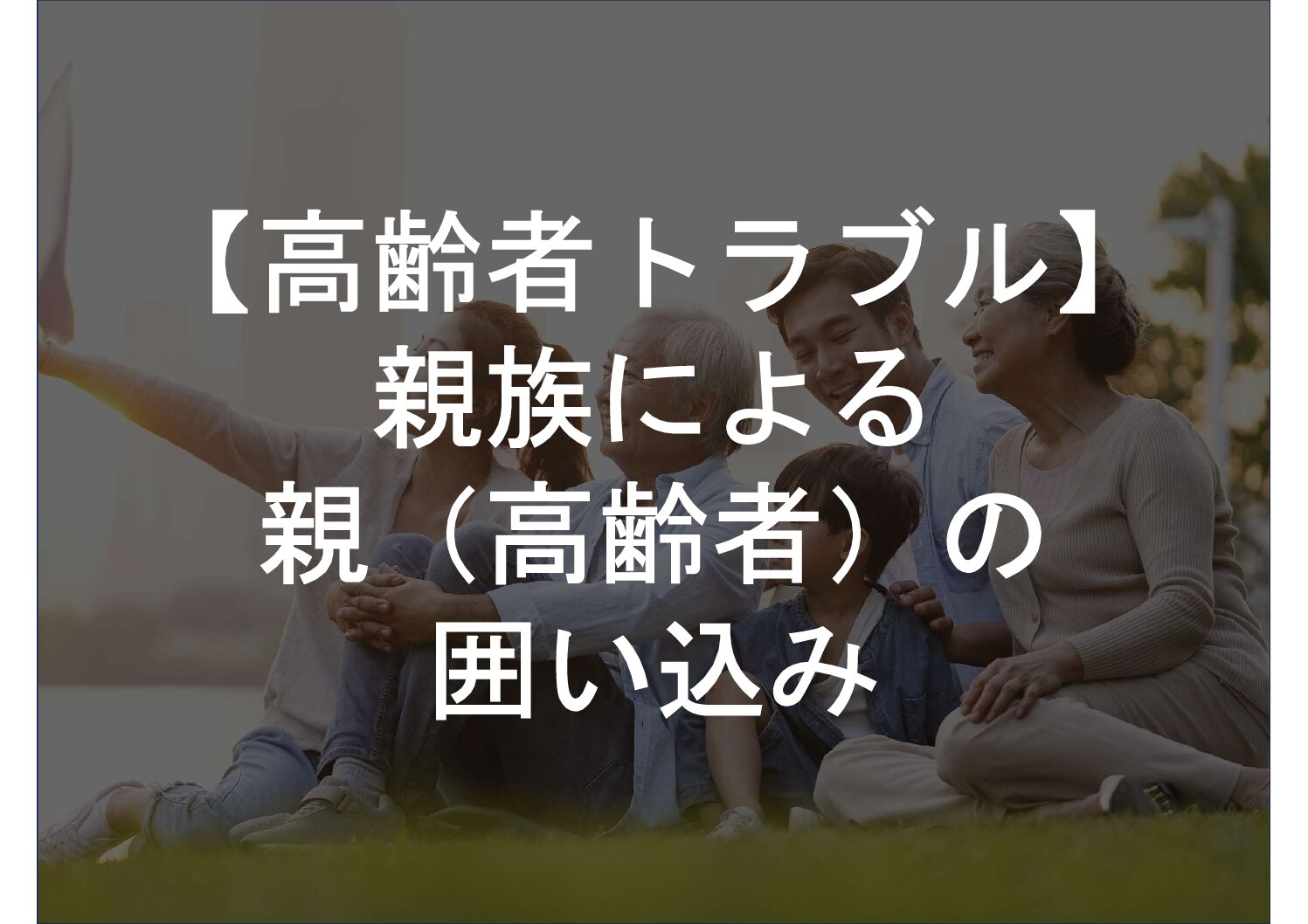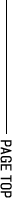Contents
令和6年6月13日、公正取引委員会より、令和5年度の相談事例が公表されております(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240613.html)。独占禁止法に関する相談事例の傾向をみることで、事業者の事業活動や取引において、近年、どのような問題が生じているのかを検討してみたいと思います。
相談内容と件数の傾向
令和5年度における一般相談(書面回答と相談内容等の公表を前提とする「事前相談制度」によらないもの)の件数は5911件となっており、令和4年度における一般相談の件数が3017件であったことと比較すると、約2倍近くまで増加しております。
一般相談の件数がそのように大きく増加した要因はどのようなものだったのでしょうか。
令和5年度における一般相談5911件のうち、事業者の活動に関する相談が5727件であり約97%、事業者団体の活動に関する相談が約3%を占めています。
その前年度(令和4年度)においても、一般相談3017件のうち、事業者の活動に関する相談が2879件で約95%、事業者団体の活動に関する相談が約5%であり、その点に大きな変化はなかったようです。
令和5年度とその前年度における事業者の活動に関する相談の内訳をみると、以下のとおりとなっております。
【流通・取引慣行に関する相談】 (R4)2631件 (R5)5414件
【-うち優越的地位の濫用に関する相談】 (R4)2094件 (R5)4788件
【共同行為・業務提携に関する相談】 (R4) 110件 (R5) 151件
【技術取引に関する相談】 (R4) 8件 (R5) 13件
【共同研究開発に関する相談】 (R4) 6件 (R5) 15件
【その他】 (R4) 138件 (R5) 183件
【計】 (R4)2879件 (R5)5727件
事業者の活動に関する相談の内訳を、令和4年度と令和5年度で比較すると、流通・取引慣行に関する相談が2631件から5414件に増加しています。
さらに、優越的地位の濫用に関する相談件数をみると、令和4年度が2094件であったのに対し、令和5年度では4788件まで約2.3倍に増加しています。
そうすると、令和5年度の一般相談件数が令和4年度と比較して約2倍近くまで増加した原因は、優越的地位の濫用に関する相談件数が倍以上に増加したことにあることが分かります。
掲載事例について
令和5年度の相談事例集においては、11件の具体的相談事例が掲載されております。
そのうち、事業者の活動に関する相談が7件、事業者団体の活動に関する相談が4件となっておりました。
令和4年度の相談事例集では、事業者の活動に関する具体的相談事例の掲載が3件にとどまっておりましたが、令和5年度の相談事例の掲載が7件に増加しました。
参考にできる相談事例が増えたことは、法適用の予測可能性を高めることができるので、有り難いところです。もっとも、事業者の活動に関する相談のうち、優越的地位の濫用に関する相談が大多数を占めていることからしますと、優越的地位の濫用に関する相談の具体的事例の紹介があると有益と考えられます。
事業者の活動に関する相談に関する具体的相談事例7件をみてみると、以下の規制行為に関するものでした。
相談事例1 新技術開発のための組合設立による共同研究開発
相談事例2 政策実現目的に向けた共同行為
相談事例3 付随業務につき共同での団体設立
相談事例4 業務見直しの取組みに関する共同宣言
相談事例5 共同購入と競合他社への全量OEM供給
相談事例6 撤退する競争業者から販売先の取次ぎを受ける行為
相談事例7 運送会社による特定路線の時刻調整
以下では、具体的な相談事例の概要を紹介しますので、今後の事業活動のご参考にして頂ければと存じます。
①輸送用機械メーカーによる二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術のための共同研究
【相談概要】
輸送用機械メーカー4社が、共同して技術研究組合を設立し、当該組合において二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術に関する基礎研究を共同して実施し、研究成果を共有することについて、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
【相談内容のポイント】
(目的)
・グリーン社会実現のための新技術(二酸化炭素を排出しない燃料を使用)の共同基礎研究を実施
・得られた研究成果を各社で共有
(背景)
・新技術の研究には多大な資源が必要であり、1社での実施は困難
・4社の市場シェア合計は約90%
(取組内容)
・技術研究組合を設立し、共同で基礎研究を実施
・研究内容は、事実・現象の知識取得と規格化課題の抽出に限定
・研究成果は組合参加者が無償で利用可能
・組合不参加者も実施許諾により成果を利用可能
・次工程の研究開発や製品開発は各社の自由
・共同研究期間は5年間
・共同研究以外での各社の研究を制限しない。
【独占禁止法の考え方のポイント】
1 独占禁止法の原則
(1)不当な取引制限の禁止:
・事業者間の共同行為による価格決定、数量制限、技術制限などにより、市場における競争の実質的制限は違法。
(2)私的独占の禁止:
・単独又は共同で、他社の事業活動を排除・支配し、競争を制限することは違法。
(3)共同研究開発の考え方:
・技術革新を促進する共同研究開発は、競争促進効果があれば問題となる可能性は低い。
・ただし、参加者間の研究開発制限や、市場競争の実質的制限がある場合は違法。
2 本件共同研究に対する評価
(1)競争制限効果の検討
・国内外において技術市場における研究開発の主体は多数存在。
・基礎研究に限定され、特定の製品開発競争を阻害しない。
・研究の必要性、対象範囲、期間も適切。
・本件事案を総合的に考慮すれば、市場シェアが高いが、技術市場又は製品市場における競争の実質的制限には至らない。
(2)他社が技術市場又は製品市場から排除される可能性の検討:
・組合への参加は開放的。
・研究成果は広く利用可能。
・他社の市場排除には繋がらない。
(3)結論:
本件共同研究は独占禁止法上問題となるものではない。
②石油化学コンビナートの構成事業者によるカーボンニュートラルの実現に向けた共同行為
【相談概要】
石油化学コンビナートにおいて石油化学製品等の製造販売を行っているA社、B社、C社、D社及びE社が、同コンビナートにおけるカーボンニュートラルの実現に向けて実施する共同行為について、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
【相談内容のポイント】
(目的)
石油化学コンビナートにおけるカーボンニュートラルの2050年の実現
(背景)
・地球温暖化対策の推進
・脱炭素社会への移行
(取組内容)
1 燃焼時に二酸化炭素の排出がないアンモニア等を燃料とする共同の発電設備等の設置及び利用等
2 製品の原材料である、基礎化学品について、二酸化炭素の排出が少な い原材料を用いたバイオ基礎化学品等に転換するための原材料の共同購 入等
3 二酸化炭素の共同回収・再利用・貯留
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 不当な取引制限の禁止
事業者間の共同行為による価格決定、数量制限、取引先制限などにより、市場における競争を実質的に制限することは違法。
2 グリーン社会実現に向けた取り組み
・基本的には競争促進効果があり、独占禁止法上問題とならない場合が多い。
・ただし、価格・数量、顧客・販路、技術・設備等を制限し、競争制限効果のみを持つ場合は違法。
・競争制限効果と競争促進効果が見込まれる場合は、目的の合理性と手段の相当性を考慮し、総合的に判断される。
・競争制限効果が見込まれない行為は、独占禁止法上問題とならない形で実施可能。
【回答のポイント】
1 当該石油化学コンビナートの取組み
カーボンニュートラル実現に向けた共同行為は、グリーン社会実現に向けた取り組みと認められる。
2 製品市場への影響
・共同行為は製品コストに影響を与えるが、競合関係がない製品が多く、競争制限効果が生じることはない。
・競合する製品についても、市場状況から競争の実質的制限は生じることはない。
3 購入市場への影響
アンモニア等、バイオマス等の共同購入は、将来的な市場拡大が見込まれ、共同購入量が限定的なため、競争の実質的制限は生じることはない。
4 結論
A社ほか4社の共同行為は、いずれも競争の実質的制限を生じず、独占禁止法上問題となるものではない。
③今後製品寿命が到来する電気機器についてのメーカーによる廃棄処理業務の共同化
【相談概要】
今後製品寿命が到来する電気機器について、電気機器メーカー12社が、それぞれ行っていた廃棄処理業務を、新たに共同で設立する団体において行う取組について、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
【相談内容のポイント】
1 目的
・今後増加が予想される電気機器αの廃棄処理について、所有者が廃棄物処理を委託しやすくすることにより確実に廃棄処理が行われるようにする。
・増加が予想される廃棄処理に効率的に対応する。
2 背景
・電気機器αは、グリーン社会の実現に資することから普及が急速に進んでいる。
・電気機器αには製品寿命があり、今後廃棄処理数の増加が予想される。
・電気機器αの所有者は、廃棄処理を法律に基づき、自らまたは許可を受けた業者に委託する必要がある。
・電気機器メーカーは、広域処理の認定を受けることで廃棄処理業務が可能となるが、単独申請では自社製品のみとなる。
・産業廃棄物処理業者は多数存在し、電気機器αの廃棄処理についても十分な供給余力がある。
3 取組内容
・12社は共同で事業者団体を設立し、広域処理の認定を受ける。
・廃棄処理希望者には同団体を案内する。
・廃棄処理に必要な最小限の情報を団体に提供し、情報遮断措置を講じる。
・団体が廃棄処理料金を決定し、所有者から料金を受け取る。
・団体は廃棄処理業務を産業廃棄物処理業者に再委託する。
・12社は、個別に廃棄処理業務を行うことも妨げない。
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 「不当な取引制限」
(1)電気機器αの所有者に対する廃棄処理業務の提供市場
・本件取組により、12社が個別に提供していた廃棄処理業務が本件団体に集約。
・しかし、12社の市場シェア合計は小さく、産業廃棄物処理業者の供給余力も十分。
・したがって、本件取組によって廃棄処理業務の提供に係る競争が実質的に制限されるとはいえない。
(2)産業廃棄物処理業者からの廃棄処理業務の調達市場
・本件取組により、12社が個別に行っていた廃棄処理業務の調達が本件団体に集約。
・しかし、12社の市場シェア合計が小さいため、産業廃棄物処理業者は他の事業者からも業務を受託できる。
・また、産業廃棄物処理業者は電気機器α以外の廃棄物も扱っており、12社が料金を自由に左右できる状況ではない。
・したがって、本件取組によって廃棄処理業務の調達に係る競争が実質的に制限されるとはいえない
(3)電気機器αの販売市場
・本件取組では、電気機器αの商品仕様等の情報が本件団体に提供されるが、情報は適切に遮断される。
・12社は引き続き独立した競争単位として販売を行うため、販売市場における競争への影響はない。
3 回答
本件取組は独占禁止法上の問題となるものではない。
④加工食品メーカーによる物流事業者が納品場所での附帯作業の見直しに向けた共同宣言
【相談概要】
加工食品メーカー4社が、物流の2024年問題の解消に向けて、小売業者に対する商品の配送において物流事業者が納品場所で行っている商品の開梱、値札付け作業、店頭での商品陳列等の附帯作業の見直しに取り組むことを共同で宣言する行為について、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
【相談内容のポイント】
1 目的
物流の2024年問題の解消に向けて、物流事業者の過度な負担を軽減し、配送効率を改善する。
2 背景
・加工食品メーカー4社は、小売業者との直接取引において、配送時の附帯作業を物流事業者に委託している。
・物流の2024年問題により、トラックドライバーの労働時間制限が強化され、物流への影響が懸念されている。
・国のガイドラインでは、荷主事業者に対して、物流事業者の負担軽減に向けた商取引の見直しが求められている。
・小売業者の指定する附帯作業は、物流事業者の過度な負担となっており、見直しによる配送効率の改善が見込まれる。
3 取組内容
・4社は、附帯作業の見直しについて共同で宣言する。
・見直しの範囲、時期、方法等は、各社が独自に決定する。
・小売業者との交渉も、各社が個別に行う。
・各社は、相互に情報共有や強制は行わない。
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 不当な取引制限
事業者が他の事業者と共同で、価格や数量、取引先などを制限し、市場の競争を実質的に制限することは違法。
2 本件取組が競争に与える影響
・附帯作業の実施は競争手段の一つとなり得るが、本件取組は価格や数量などの重要な競争手段を制限するものではない。
・各社が見直しの内容を独自に決定し、小売業者との交渉も個別に行うため、需要者の利益を不当に害するものではない。
・物流の2024年問題への対応という社会公共的な課題に対して、国のガイドラインを踏まえて行うものであり、正当な目的に基づく。
・本件取組は、社会公共的な目的を達成するために合理的に必要な範囲内であるといえる。
3 結論
本件取組は、独占禁止法上問題となるものではない。
⑤需要量が減少している工業製品に係るメーカーによる原材料の共同購入及び製品の全量OEM供給
【相談概要】
工業製品メーカー2社が、需要量が減少している工業製品について、原材料の共同購入を行うとともに、2社のうち1社が、他の1社に対して製品の全量OEM供給を行うことについて、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
【相談内容のポイント】
1 目的
・原材料αの購入規模を拡大し、安定的な購入を図る。
・工業製品Aの効率的な製造を行う。
2 背景
・X社とY社は、工業製品Aのメーカーであり、国内市場で約60%のシェアを持つ。
・工業製品Aの需要は、類似製品である工業製品Bの台頭により減少傾向にある。
・新型コロナウイルス感染症の影響で原材料αの生産量が減少し、供給遅延や取引停止のリスクがある。
・原材料αの購入市場における2社のシェアは10%未満であるが、工業製品Aの製造に不可欠な原材料である。
3 取組内容
(1)原材料αの共同購入:
・X社がY社に必要量を報告し、Y社が一括購入する。
・購入価格等の情報は購入部門に限定して共有する。
(2)工業製品AのOEM供給:
・Y社が購入した原材料αをX社に引き渡し、X社が工業製品Aを製造する。
・X社は、自社ブランドで販売するとともに、Y社向けにOEM供給を行う(Y社は自社製造を行わない)。
・両社は、工業製品Aをそれぞれ自社ブランドで独自に販売し、販売価格、販売数量、取引先等の情報は共有しない。
・工業製品AのOEM供給価格や製造数量等の情報は製造部門に限定して共有する。
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 不当な取引制限
事業者が他の事業者と共同で、価格や数量、取引先などを制限し、市場の競争を実質的に制限することは違法。
2 本件取組が競争に与える影響
(1)原材料αの共同購入
・原材料αは代替性がないが、地理的範囲は日本全国であり、2社の市場シェア合計は10%未満である。
・したがって、競争を実質的に制限するものではなく、独占禁止法上問題とならない。
(2)工業製品AのOEM供給
・工業製品Aには代替となる工業製品Bが存在するが、価格差や耐久年数を考慮し、工業製品Aを商品範囲として画定。
・地理的範囲は日本全国であり、2社の市場シェア合計は約60%であるが、需要減少や有力な競争事業者の存在、隣接市場からの競争圧力がある。
・2社はOEM供給後も独自に販売を行い、価格や数量などの情報共有は行わない。
・OEM供給価格や製造数量などの情報については、情報遮断措置を講じる。
・したがって、競争を実質的に制限するものではなく、独占禁止法上問題とならない。
3 結論
本件取組は、独占禁止法上問題となるものではありません。
⑥新規受付終了のため競合事業者に対する契約取次依頼
【相談概要】
一般消費者向けの商品を供給する事業者X社は、急激なコスト上昇のため、同商品を供給する契約の新規受付を終了することを決定しました。X社は、既存の顧客へのサービス提供を継続するため、競合事業者Y社に、一般消費者との契約の取次ぎを依頼することを検討しました。この依頼について、独占禁止法上の問題がないか、公正取引委員会に相談しました。
【相談内容のポイント】
1 目的
X社が商品αの販売チャネルを拡大する。
2 背景
・X社とY社は、A地域で一般消費者向けに商品αを供給する事業者である。
・Y社は、全国で役務βも提供しており、A地域に店舗を持つ。
・商品αは、価格競争が激しく、供給事業者は容易に参入できる。
・Y社は、商品αの供給事業から撤退する意向である。
・A地域の商品α供給市場では、X社が約70%のシェアを持つが、Z社などの新規参入により競争が激化している。
・Y社は、役務βの提供市場で約20%のシェアを持つ有力な事業者である。
3 取組内容
・Y社は、商品αの供給契約の新規受付を終了した後、X社の取次事業者となる。
・Y社は、A地域にある役務βの店舗をX社の商品αの営業活動に活用する。
・X社は、Y社が他の商品α供給事業者の取次事業者となることや、将来的に自社で商品αの供給を再開することを制限しない。
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 私的独占の禁止
一般に、有力な事業者が他の事業者の事業に係る権利等を集積することにより、他の事業者の事業活動を支配・排除し、市場支配力を形成・強化することは、競争の実質的制限となり違法。
2 商品αの供給市場への影響
(1)市場の画定
・商品αには代替的な商品が存在しないため、商品範囲は「商品α」と画定。
・商品αの供給可能な地理的範囲に制約があるため、地理的範囲は「A地域」と画定。
(2)競争への影響
・共同取組により、X社はA地域における商品αの供給市場で営業力を強化し、市場シェアを増加させる可能性がある。
・A地域にはZ社をはじめとする多数の供給事業者が存在し、X社に対する競争圧力となる。
・商品αの供給市場への参入障壁は低く、参入圧力が働く。また、Y社が他の供給事業者の取次事業者となることや、将来的にY社自身が供給を再開することも制限されない。
・商品αの供給市場では、価格を重視する需要者からの競争圧力が働く。
【結論】
本件取組は独占禁止法上問題とならない。
⑦環境変化に伴う旅客輸送会社による特定路線の運行時刻の調整等
【相談概要】
燃料費の高騰等による利益率の低下や新型コロナウイルスの感染拡大の影響等に よる利用率の低下を背景として、旅客輸送会社2社が、共同で、特定の路線について の運行時刻等の調整を行うこと、広告活動を行うこと及び必要な範囲の情報を共有す ることを内容とする業務提携を行うことについて、独占禁止法上問題となるものでは ないと回答した事例
【相談内容のポイント】
1 目的
・Y社路線の利用者数を増やし、収益を向上させる。
・X社とY社が協力して、両社の路線の乗り継ぎの利便性を向上させる。
2 背景
・X社とY社は、国内で旅客輸送業を営む事業者である。
・X社は基幹路線と地方路線を運行し、Y社は主に地方路線を運行している。
・燃料費の高騰や新型コロナウイルス感染拡大の影響で、旅客輸送事業全体の利益率が低下している。
・特に地方路線は収益性が低く、Y社は路線の廃止や事業継続の困難に直面している。
・Y社路線のほとんどはY社のみが運行している路線のため、X社とY社は潜在的には競合するものの、Y社路線の代替となるX社路線はほとんどない。
3 取組内容
(1)運行時刻の調整
・X社路線とY社路線の乗り継ぎを可能にするため、特定の路線の運行時刻の変更や増減便を共同で行う。
・ただし、運賃や座席数などの設定は各社が個別に行う。
(2)共同広告活動
・Y社路線の発着地域で、観光情報や路線利用促進のためのウェブサイトやSNSへの掲載、ダイレクトメールの送付などの広告活動を共同で行う。
(3)情報共有
・上記の取り組みの効果を高めるため、X社が必要な範囲でY社路線の情報(座席数、利用率など)を共有する。
・X社は、情報へのアクセス制限やパスワード管理などの情報遮断措置を講じ、運賃などの機密情報は共有しない。
【独占禁止法上の考え方のポイント】
1 不当な取引制限の禁止:
事業者間の共同行為による価格決定、数量制限、取引先制限などにより、市場における競争の実質的制限をすることは違法。
2 回答の要旨
(1)運行時刻の調整
・運賃等の重要な競争手段に関する調整は行わない。
・Y社路線に接続するX社路線は基幹路線であり、競争への影響は小さい。
・Y社路線では新規参入が期待されず、他事業者の排除にはつながらない。
・乗り継ぎの利便性向上と地方都市の交通ネットワーク維持に資する。
・したがって、独占禁止法上問題とならるものではない。
(2)共同広告活動
・観光情報や路線利用促進の広告であり、競争手段の情報を共有しない。
・運賃設定などの重要な競争手段を拘束しない。
・したがって、独占禁止法上問題となるものではない。
(3)情報共有
・運賃に関する情報は共有されない。
・共有情報は本件取組に必要な範囲に限定。
・X社は情報遮断措置を講じる。
・したがって、独占禁止法上問題となるものではない。
【結論】
本件取組は独占禁止法上問題となるものではない。
最後に
令和5年度の相談事例からは、独占禁止法と関連する事業者の活動としては以下の傾向がみられるようです。
1 環境問題への対応
脱炭素化の流れを受けて、企業が共同で新技術の開発や、独占禁止法との関係についての関心が高まっていることが伺えます。
2 物流効率化の促進
物流の2024年問題に代表される課題に対し、複数の事業者が連携して解決策を探る動きが見られます。これは、人手不足やコスト増加といった社会的な課題に対応するため、企業が協力せざるを得ない状況が生じているものとみられます。
3 厳しい経済状況への対応
市場の縮小や需要の変化に対応するため、企業が共同で原材料を調達したり、生産体制を見直したりするケースが増えています。これは、厳しい経済状況の中で、企業が生き残りをかけて模索している状況を表しています。
4 緊急時への対応や公共性の維持
物価高といった緊急事態やアフターコロナによる環境変化が生じる中、サービスを維持のために、競合する事業者同士が協力する必要が生じるケースも存在します。
これらの傾向から、令和5年度の相談事例は、社会的な課題への対応、事業環境の変化への適応といった、現代の経済が直面する課題を反映している事例が見られました。
企業は、これらの課題に対応するために、従来とは異なる協力の形を模索しており、その際に独占禁止法との関係が重要な検討事項となっていることが伺えます。
独占禁止法に関する相談対応をしてくれる事務所は、そう多くはないのが実情かと思われます。当事務所では、独占禁止法の遵守を始めとする御社のコンプライアンスの取組への協力や独占禁止法違反事件への対処について適切なアドバイスをさせて頂くことができますので、ぜひ当事務所にお問合せを頂ければと存じます。
Column コラム
注目記事ランキング
相談事例のカテゴリー
準備中です
コラムをもっと見る