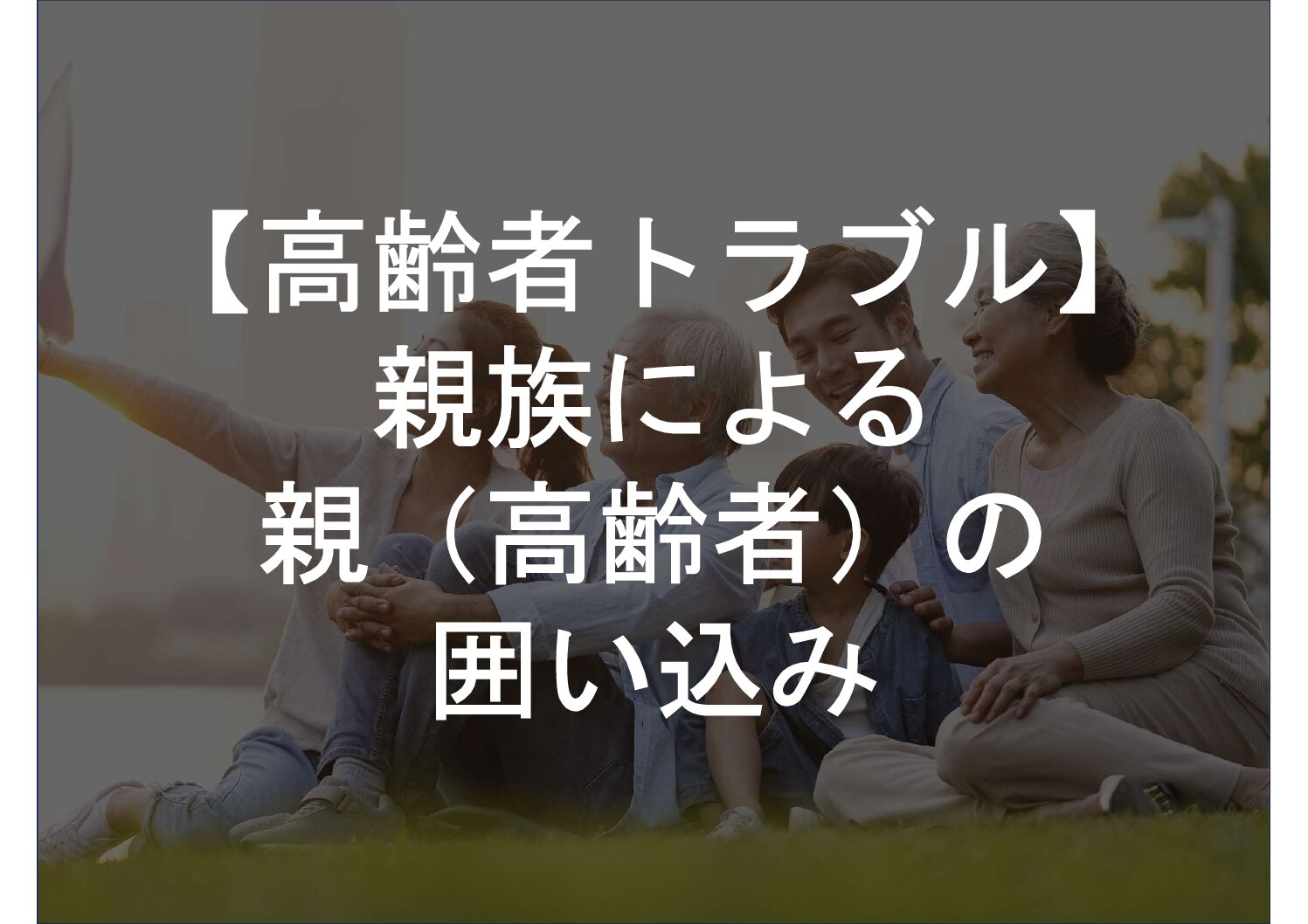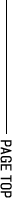Contents
優越的地位の濫用とは?!
ニュースや新聞等の報道において「優越的地位の濫用」という言葉を聞くことが増えてきましたが、それがどのような行為なのかをきちんと把握されている方は少ないのではないかと思われます。
事業者様より取引に関するご相談をお受けしていると、実際には、それが違法な「優越的地位の濫用」に当たり得るとは知らずに、そのような取引を行っていたり又は他の事業者より強いられたりしている例もございました。
本稿では、優越的地位の濫用とは、どのような場合に適用され、いかなる行為がそれに該当するのかについて、基礎から具体例を交えて解説いたします。優越的地位の濫用を正しく理解して頂くことで、自社の取引内容や取引相手との関係性を見直し、コンプライアンスに対する意識向上にお役立てを頂ければと思います。
違反被疑行為の具体的事例
まずは「優越的地位の濫用」に該当し得る行為のイメージを掴むため、違法の疑いがあるとされた具体的行為についてみてきましょう。
近年の違反被疑事件では、違法の疑いがあるものとして概要以下の行為が指摘されています。
【無償での人員派遣】
大規模な小売店が、新規開店や新装開店の際、納入業者に対し、商品の陳列作業等を行わせるため、無償で人員派遣を行わせるもの。
また、大規模な小売店等が、閉店の際、納入業者に対し、商品の返品作業等を行わせるため、無償で人員派遣を行わせるもの。
【取引と無関係な商品の購入要請】
大規模な小売店が、納入業者に対し、取引とは関係しない商品の購入を要請するもの。
【納入業者に対する費用負担の要請】
大規模な小売店が、本来自社において負担すべき何らかの費用について、納入業者に対し、事前に算出根拠等の明確な説明もなく、金銭の提供を要請するもの。
【納入業者に対する不良在庫の引取要請】
大規模な小売店が、売れ行き不振の不良在庫につき、納入業者に対し、納入業者側に帰すべき事情や返品に関する合意等もないのに、返品に応じるよう要請するもの。
【特定のサービスに参加しない業者への不利な取扱い】
ECサイトが、特定のサービスの実施に参加しない出店事業者に対し、商品検索において不利に取り扱う又はそれを告知することで当該サービスの実施への参加を余儀なくするもの。
【製造受託業者に対する商品資料作成費用の減額】
フランチャイズチェーン本部が、プライベート・ブランドの新商品を販売する際、当該商品の製造を委託する業者に対し、製造委託代金から商品紹介資料の作成費用を減額して支払うもの。
【証券会社による上場会社に不利な株式発行条件の要請】
新規上場の際の主幹事証券会社が、新規上場会社に対し、同社の説明を十分検討せず、同社の主張する想定発行価格を下回る価格等の受入れを要請することで、新規上場会社においてより多額の資金調達の実現をできなくしたもの。
【対抗価格で販売するための価格引下げ分の負担要請】
大規模な小売店が、競合店に対抗して販売価格を引き下げて販売した場合、その差額分を納入業者に負担させるもの。
【大手検索プラットフォームによる自社アプリ搭載と他社アプリ非搭載に関する契約】
大手検索プラットフォームが、端末メーカーに対し、アプリケーションストアの搭載を許諾する際、自己の検索アプリケーションを搭載させ、当該アプリケーションの端末上の配置場所を指定し、また、自己と競争関係にある検索アプリケーションを搭載しないことを条件に、検索連動型広告サービスにより得た利益を分配する内容の契約を締結するもの。
「優越的地位の濫用」に関する法規制
独占禁止法においては、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」(第19条)として、事業者が「不公正な取引方法」を行うことを禁止しています。
そして、独占禁止法では、「不公正な取引方法」(第2条9項本文)に当たる禁止行為が定められており、その一つに「優越的地位の濫用」(第2条9項5号)があります。
以下で「優越的地位の濫用」に関する条文をみていきます。
【第2条9項5号本文】
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
条文の規定からすると、「優越的地位の濫用」とは、
①「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用」して【地位要件】
②「正常な商習慣に照らして不当に」【不当性】
③禁止行為をすること【行為要件】
から構成されていることが分かります(独占禁止法第2条9項5号)。
以下、①【地位要件】、②【不当性】、③【禁止行為】を説明していきます。
①「優越的地位」とは:【地位要件】
公正取引委員会によれば、
「自己の取引上の地位が相手方に優越していること」とは、
「取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りる」
との考え方が示されています。
分かりやすく言うと、相手方との取引関係において、自己が相手方よりも強い立場にあれば、「優越的地位」にあると判断される可能性があります。
公正取引委員会によれば、「市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はな」いとされています。
そのため、市場において高いシェアを有してなくても、また、相手方との関係において事業規模に大きな格差はなかったとしても、「優越的地位」にあると判断される可能性がありますのでご留意ください。
以上の考え方を前提として「優越的地位」とは、
取引の継続が困難となれば、事業経営において大きな支障となるため、著しく不利益な要請も受け入れざるを得ないような場合であるとされています。
具体的に「自己の取引上の地位が相手方に優越していること」に該当するか否かがどのように判断されるかについては、
①相手方に対する取引依存度
②市場における地位
③取引先変更の可能性
④取引の必要性
に該当する事実等を総合的に考慮して判断するとされています。
また、優越的地位にある者が、相手方に対して不当に不利益を課して取引を行う場合には、通常、優越的地位を「利用して」行われたものと認められるとされています。
②「正常な商習慣に照らして不当に」とは:【不当性】
「正常な商慣習に照らして不当に」とは、
公正な競争秩序の維持・促進の観点から、個別の事案ごとに「優越的地位の濫用」の該当性を判断されることを意味するとされています。
また、公正取引委員会によれば、「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の観点から是認されるものをいうとされています。
そのため、通常の取引で用いられている商慣習に合致しているとしても、それが直ちに正当化されるものではないことに注意が必要です。
③優越的地位の濫用として禁止される行為とは:【行為要件】
独占禁止法で問題となる優越的地位の濫用について、具体的に禁止される行為類型ごとに、想定される違反行為や過去に違法行為とされた具体的事例を挙げて、次項において解説していきます。
ただし、優越的地位の濫用に当たる行為は、ここで挙げる行為類型に限定されるものではありませんのでご留意ください。
具体的禁止行為
購入・利用強制
条文:独占禁止法第2条第9項第5号イ
継続して取引する相手方に対し、対象とする取引とは別の商品やサービスを購入させる行為です。
相手方に購入させる商品やサービスには、自己の商品だけでなく、指定する事業者からの商品やサービスが含まれます。
「購入させる」には、購入を条件とする場合だけでなく、事実上購入せざるを得ない状況に追い込む場合も含まれます。
(1)問題となる場合
取引上の地位が優越している事業者が、取引の相手方に対し、事業遂行に不要な商品やサービス、または購入を希望しない商品やサービスの購入を要請し、相手方が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合、優越的地位の濫用として問題となるとされています。
(2)問題とならない場合
商品の製造やサービスの提供を委託する際に、品質を均一にするためなど合理的な理由で、必要な原材料や設備を購入させる場合は、問題とならないとされております。
【想定される行為】
ア 購入しなければ取引を打ち切るなどと示唆して購入させる
イ 購買担当者など取引関係に影響力のある者の要請により購入させる
ウ 組織的に要請して購入させる
エ 購入意思がない相手に重ねて要請したり、一方的に商品を送りつけたりして購入させる
オ 自社の取引先に製品の販売先を紹介するよう要請し、紹介できない場合に製品を購入させる
カ 取引の電子化にあたり、既に同様のサービスを利用しているにもかかわらず、高価な指定事業者のサービスを利用させる
【過去にみられた違法行為】
ア ホテルが閑散期の稼働率向上のため、納入業者に宿泊券の購入を要請し、断ると取引に影響すると示唆する
イ 銀行が融資の際に、金利スワップの購入を条件とする、または購入しないと不利な条件で融資すると示唆する
ウ 小売店が、販売企画の目標達成のため、納入業者やその従業員に商品を購入させる
経済上の利益の提供強制
条文:独占禁止法第2条第9項第5号ロ
継続して取引する相手方に対し、金銭、役務などの経済上の利益を提供させる行為です。
協賛金等の負担の要請
(1)問題となる場合:
協賛金等の負担額や算出根拠、使途が不明確で、相手方に不利益を与える場合や、相手方が得る直接の利益を考慮しても合理的とは言えない過大な負担を強いるなどの場合には問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
協賛金等が、負担によって得られる直接の利益の範囲内であり、相手方の自由な意思で提供される場合には問題とならないとされています。
【想定される行為】
ア 販売促進に直接寄与しない催事などの協賛金を負担させる
イ 決算対策のための協賛金を負担させる
ウ 新規オープン時に、根拠なく一定期間納入金額の一定割合を協賛金として負担させる
エ 販売目標を達成していないのにリベートを要求する
オ 広告費用を超える協賛金を要求する
カ 物流センター使用料を一方的に決定し、合理的な負担を超える額を負担させる
キ 一時的に取引を停止し、再開と引き換えに「新規導入協賛金」を要求する
【過去にみられた違法行為】
ア 小売店が、店舗の開店時に、惣菜などの納入業者に対し、根拠不明な「即引き」という名目で、通常の納入価格より低い価格で納入させる
イ 小売店が、店舗の閉店や改装時に、納入業者に、販売しない商品の返品に応じるよう要請し、返品によって生じる損失を負担しない
従業員等の派遣の要請
(1)問題となる場合:
派遣の条件が不明確で相手方に不利益を与える場合や、相手方が得る直接の利益を考慮しても合理的とは言えない過大な負担を強いる場合のほか、従業員等の派遣に代えて、これに相当する人件費の負担を強いる場合も問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
派遣が、得られる直接の利益の範囲内であり、相手方の自由な意思で行われる場合や、派遣の条件について事前に合意し、通常必要な費用を負担する場合などには問題とならないとされています。
【想定される行為】
ア 派遣費用を負担せず、自社の利益にしかならない業務を行わせる
イ 新規オープンセールで、納入業者の従業員を派遣させ、自社の商品だけでなく他の納入業者の商品の販売もさせる
ウ 派遣費用を負担するとしながら、交通費などを考慮せず一律の日当のみを支払う
エ 棚卸業務のために雇用したアルバイトの賃金を取引先に負担させる
オ 契約で定められていない倉庫内作業などを無償で行わせる
【過去にみられた違法行為】
小売店が、店舗の新規オープンや改装時に、納入業者に対し、事前の合意なく、商品の陳列などの作業を行わせ、派遣に必要な費用を負担しない
その他経済上の利益の提供の要請
(1)問題となる場合:
正当な理由なく、発注内容に含まれない設計図面、知的財産権、役務提供などを無償で提供させる場合には問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
提供される経済上の利益が、商品の販売に付随して当然に提供されるもので、価格に反映されている場合などには問題とはならないとされています。
【想定される行為】
ア 取引に伴い発生した権利を、自社との取引過程で得られたという理由で、一方的に譲渡させる
イ 発注内容に含まれない金型の設計図面を無償で提供させる
ウ 保管すべきものを取引先に無償で保管させ、メンテナンスもさせる
エ 自社の責任によるクレーム対応を取引先に無償で全て行わせる
オ 取引先に回収義務のない産業廃棄物などを無償で回収させる
不利益な取引条件の設定等
条文:独占禁止法第2条第9項第5号ハ
受領拒否、返品、支払遅延、減額など、取引の相手方に不利益となるように取引条件を設定・変更したり、取引を実施したりする行為です。
受領拒否
(1)問題となる場合:
正当な理由なく商品の受領を拒否したり、納期の一方的な延期や発注のキャンセルをしたりする場合には問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
以下のケースは問題とならないとされています。
ア 商品に瑕疵がある、注文と異なる商品が納入された、納期遅れで販売目的が達成できなかったなど、相手方に責任がある場合
イ 事前に合意した条件に従って受領しない場合
ウ 相手方の同意を得て、かつ、通常生じる損失を負担する場合
【想定される行為】
ア 売れ行き不振などを理由に受領を拒否する
イ 恣意的に検査基準を厳しくして受領を拒否する
ウ 発注後、顧客からのキャンセルなどを理由に受領を拒否する
エ 仕様の明確化を求めたにもかかわらず、明確にしないまま作業させ、納入時に仕様と異なるとして受領を拒否する
オ 一方的に納期を短縮し、間に合わなかったとして受領を拒否する
カ 不良品があったロットのみ受領しない契約なのに、他のロットも検査せず受領を拒否する
ク 性能に影響しない微細な傷などを理由に受領を拒否する
返品
(1)問題となる場合:
返品条件が不明確で相手方に不利益を与える場合や、正当な理由なく返品する場合には問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
以下のようなケースは問題とならないとされています。
ア 商品に瑕疵がある、注文と異なる商品が納入された、納期遅れで販売目的が達成できなかったなど、相手方に責任があると認められ、相当期間内に相当量の範囲内で返品する場合
イ 事前に合意した条件に従って返品する場合や、相手方の同意を得て、かつ、通常生じる損失を負担する場合
ウ 相手方から返品の申し出があり、相手方の直接の利益になる場合
【想定される行為】
ア 展示で汚損した商品を返品する
イ 値札が貼られていて剥がしにくい商品を返品する
ウ メーカーの賞味期限とは別に短い販売期限を設定し、期限切れを理由に返品する
エ プライベート・ブランド商品を返品する
オ 月末や期末の在庫調整のために返品する
カ 独自の判断による店舗改装などを理由に返品する
ク セール終了後の売れ残りを返品する
ケ 単に購入客から返品されたことを理由に返品する
コ すぐに発見できた瑕疵なのに、検品期間を大幅に過ぎてから返品する
【過去にみられた違法行為】
小売店が、店舗の閉店や改装時に、納入業者の責任ではない理由で、返品条件の合意もなく、返品が納入業者の利益にならないにもかかわらず、商品の返品を要請し、返品によって生じる損失を負担しない
支払遅延
(1)問題となる場合:
正当な理由なく、契約で定めた支払期日に支払わない場合、また、一方的に支払期日を遅く設定したり、支払期日の到来を恣意的に遅らせたりする場合は問題となります。
(2)問題とならない場合:
相手方の同意を得て、かつ、支払遅延によって相手方に通常生じる損失を負担する場合には問題とならないとされています。
【想定される行為】
ア 社内手続きの遅延などを理由に支払わない
イ 分割納入の取引で、初期納入分だけ受領し、全て納入されていないことを理由に支払いを遅らせる
ウ 検収を恣意的に遅らせる
エ 商品の使用時期を一方的に遅らせ、それを理由に支払いを遅らせる
オ 高額な製品の支払いを、当初一括払いだったものを、一方的に分割払いに変更する
減額
(1)問題となる場合:
正当な理由なく、契約で定めた対価を減額する場合、対価を変えずに仕様を変更するなど、実質的に減額する場合には問題となります。
(2)問題とならない場合:
以下のケースのような場合には問題とならないとされております。
ア 商品やサービスに瑕疵がある、注文と異なる商品やサービスが提供された、納期遅れで販売目的が達成できなかったなど、相手方に責任があると認められ、相当期間内に相当額の範囲内で減額する場合
イ 対価交渉の一環として減額が要請され、その額が需給関係を反映していると認められる場合
【想定される行為】
ア 業績悪化などを理由に減額する
イ 恣意的に検査基準を厳しくして値引きさせる
ウ 一方的な仕様変更などで作業量が増加したにもかかわらず、当初の対価しか支払わない
エ セールでの値引き分を納入業者に負担させる
オ 毎月一定の利益率を確保するため、必要な金額を値引きさせる
カ コスト削減目標達成のため、必要な金額を値引きさせる
キ一方的な都合で一部取引を取りやめ、取引減少分を減額する
ク 他店での安売りを理由に、納入価格から差額分を差し引く
ケ 消費税相当額を支払わない、または端数切り捨てを行う
コ 一方的な都合による設計変更などで納期遅れが生じたにもかかわらず、ペナルティとして減額する
【過去にみられた違法行為】
小売店が、商品の売れ残りなどを理由に、納入業者に対し、割引販売前の価格の一定割合を値引きするよう要請する
その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等
上記以外にも、取引上の地位が優越している事業者が、取引の相手方に不当に不利益となるように取引条件を設定・変更するなどして取引を実施する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
1.取引の対価の一方的決定
(1)問題となる場合:
一方的に著しく低い、または著しく高い対価での取引を要請し、相手方が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合は問題となるとされています。
それが問題となるか否かは、対価の決定方法、他の取引先との差別、仕入価格を下回るかどうか、通常の価格との乖離、需給関係などを総合的に判断されます。
(2)問題とならない場合:
要請された対価で取引する同業者がいるなど、対価交渉の一環として行われ、需給関係を反映していると認められる場合、また、セールなどのために大量仕入れをする場合のボリュームディスカウントなど、取引条件の違いを正当に反映していると認められる場合には問題とならないとされています。
【想定される行為】
ア 大量発注を前提とした単価を、少量発注の場合に一方的に適用する
イ 納期が短い発注でコストが増加したにもかかわらず、通常の納期の場合と同じ単価を一方的に適用する
ウ 特別な仕様の指示などで作業量が増加したにもかかわらず、通常の単価を一方的に適用する
エ 予算単価のみを基準に一方的に単価を決定する
オ 一部の取引先と決めた単価などを他の取引先の単価改定に用いる
カ 発注量などの取引条件に合理的な理由がないのに、特定の取引先を差別して一方的に著しく低い、または高い対価を定める
キ セール品について、納入業者の仕入価格を下回る価格で納入させる
ク 原材料費の高騰などでコストが増加したにもかかわらず、従来の単価を一方的に適用する
ケ 一部店舗のセールなのに、全店舗の納入価格を一方的に著しく低くする
コ 製造原価などの資料を提出させ、「利益率が高い」などと主張して一方的に著しく低い納入価格を定める
【過去にみられた違法行為】
小売店が、セール時に、仲卸業者に対し、事前に協議することなく、仕入価格を下回る価格で青果物を納入するよう一方的に指示する
2.やり直しの要請
(1)問題となる場合:
正当な理由なく、商品受領後やサービス提供後にやり直しを要請し、相手方が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合は問題となるとされています。
(2)問題とならない場合:
以下のようなケースは問題とならないとされております。
ア 商品やサービスの内容が発注条件を満たさない場合
イ 相手方の同意を得て、かつ、やり直しによって相手方に通常生じる損失を負担する場合
ウ 試作品の作成を含む取引で、やり直し費用が当初の対価に含まれている場合
【想定される行為】
ア 受領前に一方的な仕様変更をしたにもかかわらず、相手方に伝えず作業させ、納入時に仕様と異なるとしてやり直しさせる
イ 委託内容を確認し了承したにもかかわらず、納入後に委託内容と異なるとしてやり直しさせる
ウ 恣意的に検査基準を厳しくしてやり直しさせる
エ 仕様の明確化を求めたにもかかわらず、明確にしないまま作業させ、納入後に発注内容と異なるとしてやり直しさせる
3.その他
また、上記以外にも、一方的に取引条件を設定・変更するなどして取引を実施することで、取引の相手方に不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として問題となるとされております。
【想定される行為】
ア 商品使用後やサービス提供後に支払いを受ける契約なのに、一方的な都合により前倒しで支払わせる
イ 部品製造を発注し、相手方が原材料を調達したにもかかわらず、一方的な都合で発注を取り消し、調達費用を支払わない
ウ 機械設備の導入を指示し、発注を確約したにもかかわらず、一方的な都合で発注数量を大幅に減らす、または発注を取り消す
エ 支払期日までに割引を受けることが困難な手形を交付し、通常より高い割引料を負担させる
オ 債権保全に必要な金額を超えた高額な保証金を一方的に預託させる
カ 納期遅れや商品に瑕疵があった場合のペナルティを、相手方と十分協議することなく一方的に定め、得られたはずの利益を超える額を負担させる
【過去にみられた違法行為】
フランチャイズチェーン本部が、加盟店に対し、見切り販売をやめさせ、加盟店が合理的な経営判断に基づいて負担を軽減する機会を奪う
上記の具体例は、優越的地位の濫用の考え方を理解するためのものです。個別のケースが問題となるか否かについては、専門家にご相談ください。
最後に
独占禁止法における優越的地位の濫用について、いかなる判断基準を基にどのような行為がこれに該当し得るかについて、具体的な行為例を挙げて解説いたしました。
しかし、本稿で挙げた行為例は網羅的なものではなく、実際にはより多様な形で優越的地位の濫用が行われる可能性があります。
取引上の地位が優越している事業者が、その地位を利用して取引の相手方に不利益を与える行為は、公正な競争を阻害し、取引の相手方の正当な利益を侵害する可能性があります。
取引において、以下のような状況に生じた場合には、優越的地位の濫用である可能性があります。
(1)一方的に不利な条件を押し付けられる
(2)不当な要求を受け入れざるを得ない
(3)取引の継続を盾に不利益な行為を強要される
このような状況に直面した場合には、取引先の言いなりになることなく諦めずに以下の対応を検討してください。
証拠の保全:交わされた文書、メール、録音など、状況を証明できるものを保管してください。
専門家への相談:弁護士などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けてください。
公正取引委員会への情報提供:優越的地位の濫用が疑われる場合、公正取引委員会に情報を共有することも有効です。
優越的地位の濫用は、取引上の立場の弱い取引先から利益を一方的に吸い上げたり、取引先に一方的に負担を強いたりするもので、不公正な取引方法として独占禁止法に違反する行為です。
取引先からの不当な要求には毅然とした態度で臨み、必要に応じて専門家の支援を受けながら、自らの権利を守ることが重要です。
自社が強いられている取引が違法ではないかという場合には、速やかに専門家にご相談を頂き、また、知らずに「優越的地位の濫用」を行って後に違法行為として問われないよう、社内のコンプライアンスを見直し頂くことが重要です。
当事務所では、独占禁止法違反への対応について豊富な経験を有する弁護士が、事前のアドバイス、裁判手続や裁判外での対応策も含め、個別のご事情に沿った解決策をご提案させて頂きます。ぜひ当事務所にお気軽にご相談を頂ければと存じます。
下請法が適用される取引とは?!https://www.brainlawyers.jp/case_column/case_column_test09/
下請法:親事業者の義務・禁止行為を基礎から徹底解説!https://www.brainlawyers.jp/case_column/case_column_478/
Column コラム
注目記事ランキング
相談事例のカテゴリー
準備中です
コラムをもっと見る